
先週、つい魔が差して(笑)購入してしまったのが、Robin Wilsonという人の「四色問題」(原題は、Four Colours Suffice)。平面上の地図は必ず4色で塗り分けられるという定理(4色定理)が証明されるまでの、興奮と落胆(笑)のストーリー。主だった登場人物は次の通り。
フランシス・ガスリー (Francis Guthrie) 4色問題の発案者。イングランドの地図を塗り分けている時に、4色あればどんな地図も塗り分けられることに気付く。
ド・モルガン (De Morgan) フランシス・ガスリーの弟から4色問題を聞き、興味を持つ。多くの数学者にこれを知らせ、4色問題が世に知られるきっかけを作る。
ケイリー (Arthur Cayley) 忘れられていた4色問題を復活させ、これに関する論文を初めて書く。各頂点から出る辺が3本の場合(3枝地図)に限っても一般性を失わないことを注意した。
ケンプ (Alfred Kempe) 4色定理の証明を発表する。実は間違っていたが、11年間も気付かれずにいた。証明には失敗したものの、後の発展のきっかけとなる重要な手法(Kempe chains など)を開発した。
ヒーウッド (ヘイウッド ?) (Percy John Heawood) ケンプの証明に欠陥があることを発見する。ケンプの証明を修正して、5色あれば十分であること(5色定理)を証明する。また、平面・球面以外での地図についても考察し、示性数(Genus、穴の数、例えばドーナツ面のときは1)がpの閉局面上の地図を塗り分けられる色の個数についての公式を発見した。
ヴェルニッケ 不可避集合(どんな3枝地図も必ず含まないといけない配置の集まり)の概念を導入し、幾つかの不可避集合を発見する。
ハインリッヒ・ヘーシュ (Heinrich Heesch) 不可避集合を求めるために、放電法(discharging)を考案する。これがその後の発展の基本的道具となる。
ウルフガング・ハーケン (Wolfgang Haken) ケネス・アッペル (Kenneth Appel) と共同で、4色定理を証明する。放電法を改良することにより、およそ2000個の可約配置からなる不可避集合の存在を示した。検証にはコンピューターが使われた。この結果として4色定理が成り立つことが言える。
最終的にはHakenとAppelによって証明されたのだが、コンピューターを何千時間(?)も使って検証したというその証明には、多くの人が落胆したのだった。
この本は、4色問題についてまったく知らない人でも楽しく読める素晴らしい本。数学の知識もほとんど不要。定理らしき定理は、オイラーの多面体定理(V-E+F=2) ぐらいしかないし、これもちゃんと説明されている。中学生でも読めちゃいますね、これは。
4色定理の証明はとっても難しいが、5色定理ならそれほど難しくなく、きちんと説明されていて嬉しい。大分前にクーラント、ロビンズの「数学とは何か」で5色定理の証明は読んだはずだが、まったく覚えておらず(笑)、今回初めて理解した気分。6色定理になると、さらに易しい。6色定理は「隣国は5つだけ」レンマから直ちに出るが、このレンマ(補助定理)も、オイラーの多面体定理 V-E+F=2 から簡単に示される。
こんな感じで、いきさつやお話だけでなく、具体的に数学の内容もやさしく、かつ、きちんと説明されている。特に、可約配置、不可避集合、放電法、といった基本的概念が分かりやすく説明されていて、HakenとAppelの証明法の基本方針が理解できたのは良かった。いや、素晴らしい本ですよ。



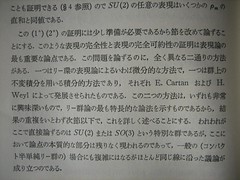
 。仮名は小さいというか、幅が狭いという感じ。なるほど。それで狭い版面に多くの情報を詰め込めるのか・・・。うーむ、恐るべし培風館。
。仮名は小さいというか、幅が狭いという感じ。なるほど。それで狭い版面に多くの情報を詰め込めるのか・・・。うーむ、恐るべし培風館。